MUSEUM TALK
著名人からの視点で語る、
「金融」への思いと明日への刺激。
人気マンガ『インベスターZ』の登場は、多くの人にとって衝撃でした。中学生が金融を学び、投資の実践を通じて、社会の成り立ちを知り、自分の位置や価値を見つめていく成長物語。年齢を問わず、投資の未経験者にも、金融や投資を身近に感じるビジネスマンにも、今の時代へ「気づき」を与え、必要な行動へと駆り立ててくれる特別な作品です。
好評のMUSEUM TALK第二回のゲストは、その『インベスターZ』の作者・三田紀房氏の登場。
ホスト役の杉山恒太郎氏の熱烈なラブコールで実現した対談は、マンガ制作の裏話から、金融教育への遥かな思いまで、話柄のつきない興味深いものとなりました。
今の時代感覚を伝えるために、
『インベスターZ』が必要でした。(杉山)

杉山 大切なキャラクターである、インベスターZの主人公・財前くんを通じて「金融/知のLANDSCAPE」に参加いただき、有り難うございます。
『インベスターZ』は2013年の7月に連載開始だそうですね。ちょうどその頃に、このミュージアムの企画が始まっていて、雑誌に登場したときに、「あ、これだ!」とすぐに思いました。ミュージアムをつくるという普遍的なことをやっているけど、この世界と繋がっていれば間違いなく今の時代の感覚で受け取ってもらえるな、と推進力になったというか。それで、スタッフみんなに『インベスターZ』にどうしても参加してもらいたいとしつこく伝えたんです。このミュージアムのレベルを、もう一歩上げるためにね。財前くんがオピニオンとしてアニメになって参加してくれ、これで勝ったと(笑)。
三田 実はミュージアムに参加してどんな感じに表現してもらえるのかがわからなかった。スタッフとは、なんか面白くなるだろうとは話していたんですが・・・。今日、実際に訪れてみてよくわかりました。あっ、こうなるのかと。展示の仕方が新しいし、展示内容も幅広いものがありますし。想像以上で驚いています。
杉山 それは、有り難うございます。
三田 『インベスターZ』は、漫画界では挑戦的な試みをしている作品です。裏話をすると、僕と今回もコーディネートしてくれたコルクという会社がすべての権利を持っています。マンガの場合、普通は出版社のライツ事業が深く関わってくるものなのですが、出版社が入ると、いろいろな手続きがあって、せっかくいただいたお話も素早く進まないことが多い。新しい試みで、どう扱われるかが見えにくいときはなおさらです。
今回のお話は、我々がすべての意思決定者なのでダイレクトにお返事できたのですが、結果としてとても良かったと思っています。
杉山 読ませていただいていて、なるほど、と思うことがたくさんあります。そのひとつに、投資のような、リスクもあるけど人生を面白くするようなものを、本来の日本人は好きだったのに、戦後になって日本人は貯蓄好きの体質と言われるようになった、というものがある。江戸とか室町とか百花繚乱で絢爛な文化やさまざまな庶民の文化があったように、もっと日本人って自由に生きていいんだよな、と読んであらためて思ったんですね。
まず金融の歴史を知ること。
そこから見えてくる事実がある。(三田)
杉山 金融の歴史について、本当によく調べて描いていらっしゃるように感じるのですが・・・。
三田 実はそうでもありません。マンガの場合は、企画を立てるときに一話目二話目の話について一通りの設計図が必要ですが、編集長がゴーを出したらすぐにはじめる。描きながら、調べながら進めていくんです。『インベスターZ』も三話くらいまでつくったらスタートしていました。
でも、この物語を始めるときに、まず歴史を知り、きちんと歴史を整理しようと思いました。というのも、企画段階で調べていると、以外と一般の人たちって世の中の歴史、とくに経済について知らないということが分かった。僕も含めて。身近なわかりやすい例で言うと、トヨタなどは、はじまりは織機をつくっていたわけですよね。それをほとんどの人は知らない。
杉山 そうか、豊田佐吉のことは、若い世代はもう知らないんですね。
三田 ソニーが戦後生まれの会社であることなんかもです。何がどうして生まれて、どうなってきた。みなさん、そうしたものをほとんど知らない。だから、連載の最初に、明治維新があって、新しい国が出来て、殖産興業があって、さまざまな会社が生まれた時代から知ろう。きちんと整理して、読者に一通りは現在の日本の経済の成り立ちを伝えていこうという気持ちがあった。で、『インベスターZ』の 舞台となる130年くらいの伝統校、道塾学園が生まれたわけです。
杉山 そうなんだ、道塾学園、実在しそうに感じましたよ(笑)。
三田 舞台も、どうしたらリアリティがあるかなと考え、北海道や九州とかだったら、当時、炭坑とかで一発当てた人がいそうだなと。フロンティアのイメージもあるし(笑)。
杉山 天才少年たちが秘密基地みたいな部屋に集まって投資をやっているでしょう。ああいうの個人的に好きなんですよ。秘密基地や秘密結社とか。あの部屋にもヒントがあったんですか?
三田 最初のフォーマットは創立者がお金を出す、それを子どもたちが運用する。そのフォーマットに何かミステリアスな部分が付加できないかと思い、各学年の一番の子が集まって秘密の投資部というものを運営することを考えました。部室の舞台としては、いわゆるオフィスのように机が並んで照明があるだけでなく、そこにでっかい金庫があるといいなと。金庫を開けると各時代の先輩たちが購入した絵画が並んでいたりする。マンガですから(笑)。そういうロケーションのビジュアルを想定して全体のデザインを考えたんですよ。
杉山 銀行の金庫ってすばらしいですよね。以前に、ある大学のサテライト校舎をつくるお手伝いをしたとき、横浜の中区に在った歴史ある銀行の建物を使うことができた。そこに入るのは映画学科だったこともあり、昔の巨大な金庫をそのまま校内のデザインとして活かして使われていますが、なんともいいですよ。SMBCにも、この春に昭和初期の建物を保ちながら改修された大阪本店の地下にある貸し金庫は、100年近い歴史を感じる場所で、その金庫の扉も数十センチある円形のもの。まさに映画の世界です。
三田 巨大な金庫ってちょっと感動しますよね。人間には、あそこに不思議な魅力を感じる潜在意識があるような・・・。
杉山 不思議な高揚感がね(笑)
日本の子どもは、実は貯めて使うのは上手い。
でも、その先を考える方法を知らない。

杉山 三田さんとお会いしたらお聞きしようと思っていたことだけど・・・先日、老舗の旦那集が集まるなかなか気高いところから講演に呼ばれて、合間にここのミュージアムのことも少し話したんです。すると、みなさんとても興味を持って下さった。老舗の旦那集がこぞって日本の子どもたちの経済的な学習能力を心配しているわけ。そのときどなたかが、「君さあ、最近の欧米の貯金箱の話を知っているかい?」といわれた。その方が言うには、子供が使う貯金箱に、社会貢献への入り口、自分への貯蓄、3つ目が将来への投資、という三つの穴があると。「同じ貯金箱なのに三つ穴があるんだよ!」と。そういえば昔聞いたことがあるなと、ふと思ったんですけど。
後で調べると、たぶん、3Sと言われるもので、Spend(使う) Share(寄付する) Save(蓄える=将来へ)ということの進化型だと思います。いずれにしても、使うか、なぜ蓄えるのか、どう使うのかが、自然に育っていくものですね。小さいときから貯金箱自体にそんなものがあると、かなりお金というものを自覚的に感じて生きていける。お聞きになったことありますか?
三田 それははじめて聞きました。でも、とくにアメリカなどは、自立自存、自分のことは自分で、ですよね。建国以来、そこの部分を教育してきた国ですから、そういうものが浸透していると思います。
『インベスターZ』にも描いていますが、実は日本人の子供ってお金を使うことは上手なんです。ちゃんと貯めて、ちゃんと使って、ちゃんと残す。この3つの段階をきちんと踏める。例えば欧米の子なんかだとお金をもらうとまず使う。日本の子供はまず貯めるという習性がある(笑)。
僕は、日本のマンガがなんでこれだけの「マンガ産業」になっているかというと、子どもたちが自分のお小遣いを貯めて、毎週本屋でマンガを買ったことも要因のひとつだと思っているんです。
杉山 なるほど、子どもたちの習性でこれだけの市場になったと。
三田 そうです。日本の子どもは、貯めて使う、というあたりまではものすごくポテンシャルが高い。でも、貯まったお金をどうするかというと急激にみんな止まってしまう。それを何かに投資したり、何かに役立てて、何がしかのリターンを得るという・・・もうひとつその先の段階がまったくない。
先日、あるテレビ局が僕に取材に来て、夕方のニュースの特集で流したいということでインタビューしてくれました。子どもたちに金融や投資をいろいろ勉強してもらう活動が、銀行や証券会社などいろいろな所で起こっている。それに絡めて、僕のマンガも紹介したいということだった。OAを見ていると、凄くよくまとめられた映像でした。僕へのインタビューも使っていただいて。でも、それが終わってスタジオに戻ったときに、スタジオのアナウンサーが、「でも、子どもたちにこんなことを教えるのは、どうか?」「子どもたちにはお金本意の人生を送って欲しくない」などといいだして(笑)。
杉山 もうねえ(笑)。そういう人たちって、お金は汚いものだとか、触るものじゃないとか、そういう風に育っているから。それだといつまでたってもお金の使い方が下手なままだよね。お金に対していつも緊張している感じがする。
三田 番組を見ていた人たちも、せっかくこれからの子どもにはこういうことも大事かも、と思っていたはずなんですよ。社会全体がリスクというか、どこかに投資したら投資先に何かあってお金が返ってこなくなるという、損害への危機感がすごくウエイトが高い。確かに100万円投資してそれが0になったら凄く傷つく。でも、それは何かを得るためのひとつのチャレンジでもある。リスクをとってチャレンジする、という風にもうちょっと雰囲気が変われば・・・。投資というものに対して社会がもう少し認めてくれるものにならないかなと。
杉山 やっぱり一種のアントレプレナーシップ=起業家精神が育ってくる要素とはそういうものです。単純に金儲けとかではなく、新しい産業を興すとか、もうちょっと抽象的に言えば新しい付加価値をつくるとか、というのも投資だよ。というふうに社会全体がなればねえ。自分のわかることしか投資できなかったらやっぱりAppleとかGoogleは生まれない。
早い段階で、社会に出て戦うための
手段をいくつか知っておくべき時代。

三田 日本人って、基本的に小学校のころから高校まで、もっといえば大学まで、生まれてからほぼ22年間、大切に与えられ続けて生活をする。お小遣いがあって、お弁当があって、先生はカリキュラム通り教えてくれて。それが学校を卒業するといきなり、さぁお金を稼げと世に出される。「今日からきみ自分で稼いでくれ」といわれたら、それは人生のギャップみたいなものを感じるし、ストレスというか、人生にかなりの打撃になると思うんです。
杉山 そのとおりですね。過保護に育てられて、いきなり世知辛い世の中で頑張れっていわれたらやっぱりパニックになりますよね。
三田 少し前倒しして中学校くらいから、自分が生きていくために何が必要か、わかりやすくいえばお金っていうのも大事なのだと。大事なものを、少し前から自分で手に入れる方法を教育のカリキュラムに入れたほうがいいんじゃないかと思うんです。自分で手に入れて自分で生きていくための必要な材料を何個か持たせたうえで「さぁ、自分で稼いでください!」というふうに教育のシステムを変えていったほうがいい。いきなり崖から突き落とすより、武器をいくつか使えるようになってからにしませんかと。
就活中の学生に相談されたときに「どこいきたいの?」と聞くと、だいたい給料の高い会社や業種とリンクしています。テレビ局とかエネルギー関係、商社、航空業界。世の中に裸で出されるものだから少しでも所得が高い場所にいかなきゃと彼らは思うんですよ。それは、わかりますよね。強迫観念です。出される身にもなってみろと。
世に出る準備をしておけば、これから伸びる産業はこれだとか、しばらくすればもっと豊かなことができる、見つけられると考えて就活をする学生が増えると思います。
杉山 よくわかります。本当は、投資という言葉が単純な金儲けとかだけでなく、ちょっと抽象的になりますが、自分のために何か新しい価値を得ることや、何かに新しい付加価値を付けることのようないろんな意味があることを知っていれば、視点も変わるだろうし、それを実現するための手段も知ることになる。就活もきっと変わっていきますね。
そのためにも、このミュージアムを中高校生たちにも利用してもらいたいと思うな。
今日は有り難うございました。
次回ゲストは、旅から金融を学んだ作家、渡邉賢太郎氏です。
対談の公開は12月10日頃を予定しています。


杉山 恒太郎
株式会社ライトパブリシティ 代表取締役執行役員社長。大阪芸術大学 客員教授
1999年より電通においてデジタル領域のリーダーをつとめ、インタラクティブ広告の確立に寄与。トラディショナル広告とインタラクティブ広告の両方を熟知した、数少ないエグゼクティブクリエーティブディレクター。


三田紀房(みた よしふさ)
1958年生まれ 岩手県出身。大学卒業後、一般企業に就職したのち、漫画家へ転進。「東大受験」をモチーフにした異色作『ドラゴン桜』で社会現象を巻き起こし、2005年第29回講談社漫画賞(一般部門)を受賞。また、高校球児を描いた『クロカン』、『甲子園へ行こう』など野球漫画も得意とする。現在は、投資漫画『インベスターZ』と高校野球ストーリー『砂の栄冠』の2本を連載している。
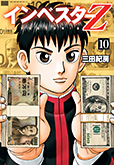
インベスターZ
金融・投資をテーマにした三田紀房氏の作品。講談社「モーニング」誌に2013年28号から連載中。主人公は、北海道札幌市にある進学校道塾学園に入学試験満点の成績で入学した中学一年生・財前孝史。彼が学校の運営資金を稼ぎだす秘密のクラブ『投資部』に入部し、そこで投資の実践を通じて金融・投資とは? を学びながら成長していく姿を描く。





