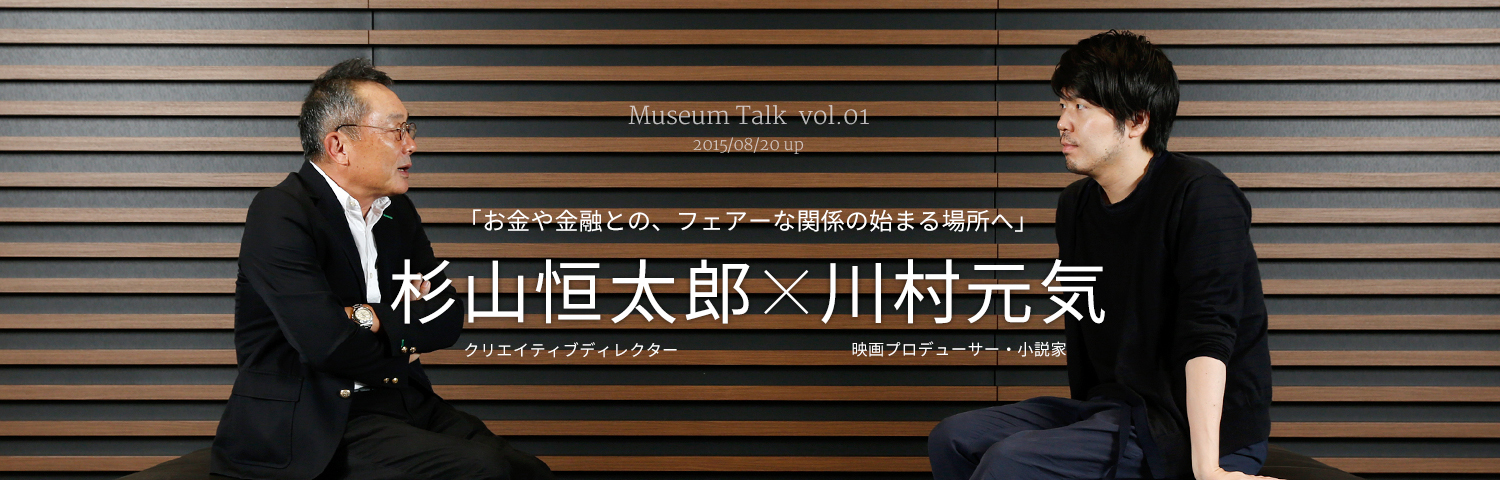MUSEUM TALK
著名人からの視点で語る、
「金融」への思いと明日への刺激。
川村元気さんといえば、日本を代表する映画プロデューサーであり、小説家としても注目される才人。
お金と人の幸福との関係を見つめた第2作目となる小説『億男』も、
若い世代を中心に、いま読んでおきたい本として支持を集め、本屋大賞にノミネートされたのちに16万部を超えるベストセラーとなっています。
MUSEUM TALK第1回目は、「金融/知のLANDSCAPE」にもオピニオンリーダーとして映像参加していただいた川村元気氏がゲスト。
本ミュージアムを企画したクリエイティブ・ディレクターの杉山恒太郎氏との対談でお届けします。
金融ミュージアム誕生の裏話から、いまの小中学生に感じてもらいたいお金との対峙の仕方まで、2人の話は多岐に渡りました。
カタチのない情報も、
体験してもらえればミュージアムになる

杉山 先ほど、体験していただいた感想は、どうでしたか?
川村 テクノロジーがスゴいですね。僕は映画人なので、S・キューブリックの映画「2001年宇宙の旅」を思い出すのですが、人類の英知と言うか、象徴というか、巨大な方形のタッチパネルがあって、あの場自体がアートにもなっているのがおもしろかったですね。
杉山 あれ、映画と同じようにモノリスと呼んでいます(笑)。いわゆる8本の知の柱。実は以前、仕事でワシントンにいったときに、NEWSEUMというニュースの歴史情報を展示したミュージアムを見に行ったことがあった。そこがとても良く出来ていてね。アートじゃなくてもミュージアムということでくくれば、カタチのない情報を展示することが出来ると、ずっと思っていました。
今回、お金と金融というのは、実は人間のことを語れる題材だから面白いと思ったんです。この時代だから、地域貢献・特に千代田区の生徒たちに楽しんでもらう、ということもテーマの一つだったので、金融ミュージアムを、その情報を学ぶだけでなく、小中学生くらいの子供たちにも、金融やお金を考えるきっかけというか、何かリアルな体験になるような場所にしたいと思って考えたんだけど・・・・。
川村 それはとてもいいですね。実は、僕自身もお金に対して苦手意識がありました。お金って、堅苦しいというか、日本人はなんか話題にしたがらないというか。日本人のお金に対する捉え方ってナローなところがあるでしょう。
杉山 川村さんの世代でもそう?
川村 多くの人がそうだと思います。お金って、人間が発明し、生んだものですから、非常に人間的ですよね。嫌いな人は嫌いでいいと思うし、好きな人は好きでいいと思うんです。ただ、それを選べるということが大事。一義的に好きとか嫌いではなく、お金の全体を見知ったうえで、お金とどう付き合うかを決めて欲しい。
杉山 知らないで急にあぶく銭が入ってきたりすると、パニック起こすし、崩壊しちゃうしね。
川村 だからお金に対する自分の苦手意識からスタートして、2作目の小説『億男』を書きました。僕は、小説を書くときは、自分が知りたいこととか、自分が苦手なものを書くと決めているんです。最初は、死について凄く恐怖があったから死について考えた『世界から猫が消えたなら』という小説を書きました。その次に、お金が苦手だったから、お金と人間の幸せについて考えてみようと。
お金はジャングルのようなもの、知らない方が危険。
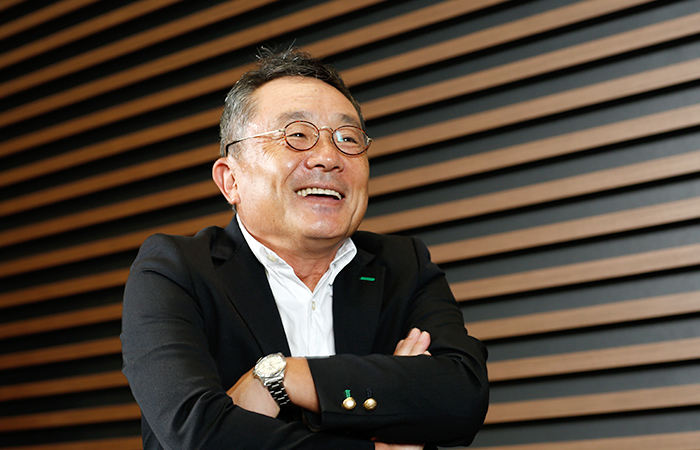
杉山 『億男』、とても面白く読みました。
川村 有り難うございます。小説を書き終わってから思うことですが、お金って、知らないほうが危ないものですよね。この2年間、小説の準備のためにお金を知ろうとしました。それはカタチや重さを測ることから始まり、偉人たちのお金にまつわるアフォリズムの収集、億万長者へのインタビューなど、本当にいろいろなことを。それで思ったのは、お金それ自体は宗教画みたいなものだな、ということ。ものすごい信仰に支えられている。でも一方で、ただの紙でもある。その紙や金属に、人を信じたいという気持ちを託して流通させている。
杉山 厳しいよね、小説の中で人を信じるという気持ちを試されているというのか。小説を読んでいて、いくつも身につまされる個所がありました。つい自分に照らし合わせてみるというか。
川村 お金が鏡みたいなものですからね。
杉山 さきほど、お金に関わるアフォリズムを2年間、集められたといわれていたけど。
川村 ありとあらゆる偉人たちの言葉を2年間、集めましたね。このミュージアムにもアフォリズムがたくさん展示されていますけど、どれもよく知っています(笑)。120人くらい億万長者といわれる人にも会って、取材しましたので、その人たちの言葉も集めました。
お金にまつわる言葉って、人間の本質が出てきます。言葉自体も面白いし、言葉と矛盾した本人の行動も。こんなにも人はお金のことを知ろう、理解しようとし、同時に、それに振り回されている、その歴史を繰り返しているのかと思いました。
お金って、ジャングルと同じですね。知らないと怖いし、知ると大分怖さがなくなるし、対応できるようになる。
杉山 いまおっしゃった、ジャングル的な感じはよくわかる。小中学生が、このミュージアムにある8本のモノリスにある金融のさまざまな情報と向き合って、金融のジャングルのことが少し怖くなくなるように機能をしてくれたらいいのだけど。とくに彼らがお金に対してフェアーに向き合えるきっかけになってくれるといいなと思っているのですが。
川村 面白いですね。でも体験してみて、少しストイックだとも思いました。もう一個くらいおまけがあるといいかもしれません。今の子供たちって、面白いガジェットに囲まれているから、もう一個、自分のこととして感じてもらうために、なにかあるといいかなと。
杉山 銀行の中にあるミュージアムだから、少しストイックです(笑)。でも、それに近いのが、川村さんと同じようにオピニオンリーダーとして参加し、動画で自分にとってのお金を語ってくれているインベスターZというマンガの主人公・財前くんかな。財前くんの設定は中学生だし、子供たちには、あそこから入ってもらえるといい。すると、ストイックな部分から、僕が目指しているエンタテインメントに近づいてくれるかもしれません。
川村 そうですね。やはりエンタテインメントがないとストンと落ちない。『億男』を書こうとしたときに、本屋に調べにいくと、お金持ちになるための手段の本が無数にあるわけです。で、疑問がわいてくる。そもそも、みんなそんなに大金持ちになりたいと思っているのかなと。僕の場合は、知りたいのはお金と人間の幸福の関係であって、そういうことを教えてくれる本は全然ない。だから、ないものを書くためには、エンタテインメントで伝えなくてはと思いました。
杉山 そういう意味では、マンガ「インベスターZ」の財前くんと一緒にすると申し訳ないけど、川村さんが出てくれたことも、エンタテインメントとしての入り口として機能してくれると思う。この2つの存在は僕にとっては大きくて、小中学生も入ってこれる入り口が2つできた、と。
子供たちが自分で考え、語りはじめる場となるために。
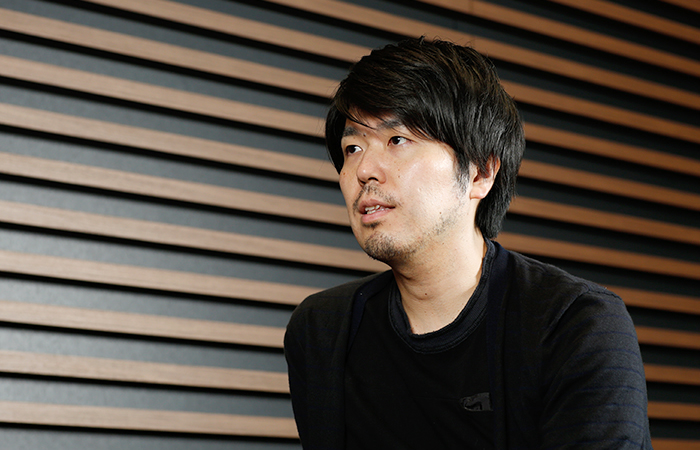
川村 『億男』には、モロッコのマラケシュがキーワードで出てくるんですけど、あの街はモノであふれている。モノだらけ。でも、クルマで少し移動するとなにもない。人間の欲望丸出しの場所と、何もない所が同じ数キロのなかに存在している面白さ。あのコントラストがスゴい、とても人間的な場所です。
杉山 大好きな映画「シェルタリング・スカイ」のテーマ、人間の無為というか。
川村 モロッコを小説に出しているのは、僕の体験が入っています。小説の取材中、バックパッカーとして、モロッコ人のラクダ乗りと2人きりで砂漠で寝るような旅をしたのですが、そのときに僕の命は、はじめて会ったモロッコ人との信頼関係で、かろうじてつなぎ止められているだけで、このラクダ乗りが逃走したら僕は死ぬな、と感じた。このときに、はじめてお金と人間との関係は、その事を拡大しているだけなのだと思った。お金のシステムというものがはっきりみえたと感じました。ホントに微妙に、国とかシステムとか人を、信頼してみようということに繋がる関係。
杉山 こんな情報の密度でできている金融ミュージアムは、他にないと思うんだけど、仮に中学生とかが、ここで体験したことで、川村さんのように何かに気づいてくれるとうれしい。お金って自分自身だし、自分の中にある懐疑心とか、人を信じる気持ちと対峙していくこと、というところまで伝わるとよりいいのだけど。
川村 そのためには、もっと能動性がいりますね。いかにも勉強というかたちで身構えるより、なるべく自分ごとにしていくように考えるべきだと思います。その意味で、子供たちが、お金の物語に対してどう反応するか。どういう結論を持つか、とても気になります。たとえば、体験した中学生などに、お金って何だと思いますか? というのを聞いて、その意見を集めてみたい。
杉山 とても面白いね。ミュージアムは広告みたいに3ヶ月のキャンペーンで終わるものではないし、進化し成長させていくことができる場所。そういうアイデアで育てていければいい。
川村 ぼくたちが気づいていない言葉を子供たちが出してくれると思うんです。僕はお金をさんざん調べて人に話も聞いて、なんとなく「人を信じることの象徴」かなと思ったけど。
杉山 そこからだよね。彼らが体験した事を人にどう話をしてくれるかとか。学ぶということは、人に話をしたり教えることが最大の学びに繋がるともいうしね。何か装置や仕掛けをつくるということだよね。いいヒントをもらったな。
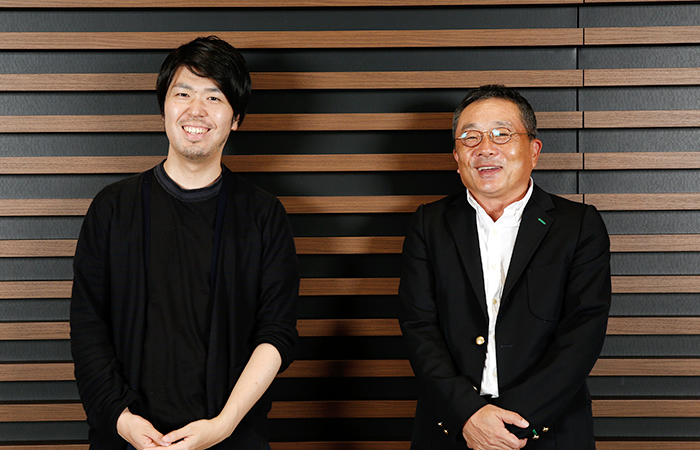


杉山 恒太郎
株式会社ライトパブリシティ 代表取締役執行役員社長。大阪芸術大学 客員教授
1999年より電通においてデジタル領域のリーダーをつとめ、インタラクティブ広告の確立に寄与。トラディショナル広告とインタラクティブ広告の両方を熟知した、数少ないエグゼクティブクリエーティブディレクター。


川村 元気
映画プロデューサー、小説家
1979年生まれ。『告白』『悪人』『モテキ』『バケモノの子』等の映画を製作。優れた映画製作者に贈られる「藤本賞」を史上最年少で受賞。初小説『世界から猫が消えたなら』が本屋大賞ノミネートを受け、80万部を突破。その他の著書に、宮崎駿や坂本龍一ら12人との対話集『仕事。』、二作目の小説『億男』がある。
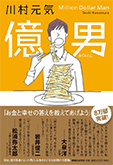
小説『億男』
マガジンハウスより発売中