MUSEUM TALK
著名人からの視点で語る、
「金融」への思いと明日への刺激。
「生命誌」という言葉をご存知でしょうか。
人間も含めた様々な生きものたちの「生きている」様子を見つめそこから「どう生きるか」を探す知の領域のこと。
38億年の生きもののつながりを見つめる学問は、金融の現在にも多くの示唆を与えてくれます。
今回のゲスト、日本の科学界を代表する中村桂子氏は、その「生命誌」を生んだ人。
中村氏の視線に映る金融の現在とは?
以前より中村氏の大ファンである杉山恒太郎氏が迫ります。
言葉が見つかった瞬間に、
前が開けることがある(杉山)
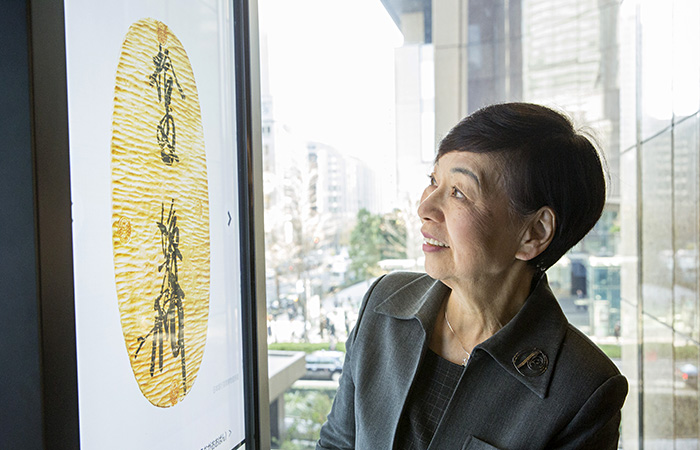
杉山 今日は、お忙しいところを、ありがとうございます。
実は、ボクは中村さんの「生命誌」の大ファンで、提唱されたとき、「生命誌」の「誌」をごんべんにされたことが、とても新鮮だった思い出があります。しかも、いま時代が追いついてきたというか、もっとリアリティーをもって、「生命誌」の捉えかたに説得力を加えていると思うんです。
中村 有り難うございます。1980年代後半、生命科学が生きものを機械のように見ることを考え直したかったのですが、具体的な知のカタチが浮かびませんでした。
そこへ「ゲノム」という、ひとつの細胞の中にあるDNA全体が見えてきて、「これがやりたかったんだ」と思い「生命誌研究館」という6文字がパッと頭に浮かびました。ですから、「生命誌」という分野だけでなく、「研究館」という場所とセットなんです。
「生命誌」を行うには「研究館」でなければいけない。この言葉が出た途端に、もやもやが消えました。
杉山 前が開けたということ?
中村 整理ができて、パッと見えたんです。「あっ、これをやればいいんだ」って。
それ以来、言葉ってすごいなと思っています。
杉山 言葉で規定した瞬間にイメージが湧くんですよね。
中村 そのとおりです。言葉はコミュニケーションにも大事ですけれど、考え、イメージを作るときに言葉が大事です。そこにいる犬は言葉がなくても示せますけれど、犬が存在しないときに「犬」を考えるには、言葉がないと考えられない。生命科学は、生きものを機械のように見るので、分析して、構造と機能が分かれば分かるという考え方ですけれど、そうではないと思っていました。科学としてどういう切り口にすればよいのかと思ったときに、「生きものって生まれるんだ」というあたりまえのことに気づきました。生まれるのですから、親がいて、そのまた親がいて……ずっと。生きものは歴史を見なければいけないはずです。しかも、幸いなことに当時、ゲノムが分かってきて。
杉山 ゲノムとはイコールDNAでいいのですか。
中村 ゲノムの実態はDNAです。当時はDNAを分析して遺伝子として見ていたのです。ところが、研究が進み、個別の遺伝子を調べるのでなく、ゲノムという総体(DNAすべての遺伝情報)を見ようという動きが出てきました。わたしの身体をつくっている細胞には必ずゲノムが入っています。わたしのゲノムを調べれば、わたしの歴史が書いてある。アリを調べればアリの歴史が書いてある。あらゆる生きものは38億年前に海で生まれた細胞を祖先にしていますので,それ以来の歴史が調べられる。こんな素晴らしい切り口があるのに、これを使わない手はないと思ったのです。そこで「生命誌」です。
杉山 普通、歴史の「史」ですよね。
中村 「史」は学校で習った歴史のイメージです。織田信長が光秀に討たれて、光秀が天下を取るかと思ったら秀吉、その後に家康というように、トップというか、時代の表層で語っていく。それは、生きものでいうなら、人間へ向けての流れだけを見ていることになります。大河ドラマですと、農民も女性も出てきますね。生きものなら、アリもいるし、ゴリラもいる。本当に多様です。それらをみんな語りたいとしたら、「史」では駄目なのです。
杉山 「史」では、収まりきらない。
中村 フランスの詩人で小説家のジュール・ルナール(Jules Renard,1864〜1910)に『博物誌』という詩集があります。
原題は、Histoires Naturelles、英語ではNaturalhistoryですね。
「誌」は、その翻訳です。生きもののこと考えるとき、人間だけを偉そうに見ていくのではなく、アリだって大事でしょう、という気持ちを込めて、この「誌」にしたのです。
杉山 言葉が見つかった瞬間に前が開けるっていうのは、僕も言葉に関わる仕事しているので、時々は起きる。今日も見ていただいた金融ミュージアムも、「金融」と「ミュージアム」というのは僕の概念ではすごく遠かったんですが、ひとつにすると、何をしていいかが、やっぱり分かったんです。確かに金融もお金も、とても人間の歴史に関係するし、実はすごく、人間そのものみたいなものでもあるっていうふうに、だんだん・・・。
もちろん、ここは三井住友銀行なので、三井と住友という両者の歴史をずっとたどっていくと、日本の産業の歴史も語れるし、日本そのものの歴史も語れる。
中村 ミュージアムで見せていただいた貨幣の歴史など、その国の様相も表していますね。それを見ていると、文化だと思いました。
杉山 そうなんです。だから、これをやらない手はないと(笑)。
社会を動かすのは人間が主体である。
それを知るためにも子供のころからお金を知るべき
(中村)

杉山 お金に関して日本では、小さいとき、子供のとき、子供はお金をあまり触るものじゃないといわれますよね。
中村 私もそうでした。先ほどのミュージアム体験で、戦後に金属がないから、陶器でつくった貨幣がありました。年代を見ると、わたしは9歳の頃なのですけれど、全然覚えていません。子供の頃、お金に触れていないんですね、きっと。
杉山 なるべく、子供には、お金と関わりを持たせない。
ところが、人生のある時期から、突然お金が出てくるから、多くの日本人はお金に対して不自然な対応をするところがある。だから、東京の千代田区の大手町で、千代田区の小学生、中高生が気軽にこのミュージアムに来て、早い時期からお金とか金融のことを体験してもらう。そういう場にもしようという意図もあります。
中村 わたしも、なんにも知らないものですから、先ほどの体験がとても楽しかったです。どこを触っても「ええっ」という感じで。
杉山 それは、教養がおありになるから、時間をかけずに慣れ親しむことができるんだと思うんです。
中村 いえいえ、知らないことだらけなので、いろいろ触りたい、押してみたいと。
杉山 それはうれしいな。
中村 子供と同じです(笑)
杉山 そういうふうに、みんなが触ってくれて、本来の金融の意味や役割を感じてもらえればと、心から思いますね。
いま、金融でつくられていることばというのは、金融資本主義とか、貨幣資本主義、カジノ資本主義とか、あまりいい言葉がないでしょう。
中村 社会を動かすために、お金は必要なものであることはよく分かります。ただわたしの立場で言わせていただくなら、主体は人間です。小学生の頃からお金や金融のことを教える必要があるとすれば、人間がお金をどう使うか、どう動かすかということの主体になれるようにしていただきたいのです。社会を考えるときに、「お金が動いてればいいじゃない」というのではなくて、人間が皆きちんと生活していくために、「お金、うまく動いていますね」と感じる社会がいいなと思うのです。子供のころからお金を学ぶとしたら、学ぶ理由はそこにあると思うのです。
杉山 そうですね、ほんとに。
多様肥大する金融経済に、
人間は「交換」する動物であることを忘れない意味。
中村 わたしたち、最初は交換、物を交換していましたよね。その交換のシステムを便利に見事にしたのがお金でしょう。
杉山 そうですね。
中村 わたし、なんでも生物に戻しますけれど、交換ということがきちんとできるのは人間だけなのです。例えば、食べ物。リスなど秋に採った食べ物を、みんな自分のために貯めて、それを何かほかのものにしようとか、誰かに分けてあげるという感覚がありません。沢山あるから少し分けてあげようとはしない。もうこんなに食べられない、というときでも、分けてあげようとも、ほかのものと換えようともしないで腐らせてしまう。
一方では、お腹をすかした仲間もいるわけです。だから、交換ができるのは、人間のすばらしい能力です。しかも、等価交換っていうのか、おにぎりと柿の種のように、違うものにお互いが価値をつくっていく。一方の人には価値がなくても、もう一方の人に価値があれば、違うものでも交換できるわけです。そういうことが、お金が生まれる要因のひとつだと思うのです。
ただ、物を交換する時は必ず心が付いている。心の交換っていうか、心の交流が必ず、伴ってくる。ほかの動物にはそういうタイプの心の動きがないから交換をやらないわけですね。人間は心があるから、「交換しようね」といって、相手のことを思ってやったことが、お互いに利益になる。お金にも、その本質は付いているはずだと、わたしは思っているのですが、お金になった途端に……。
杉山 心が離れていく。
中村 最初は付いているんでしょうね。
杉山 どんどん、どんどん、抽象化されて、肥大化していったので……
中村 お金だけで動くようになりましたね。最近は、心抜きのところでお金が動いていることが多いように思います。どんなに大量のお金であろうと、心と一緒に動くようにしないと、人間が主体で社会が動いていることにはならないのではないかなと思って。
杉山 ポストモダンの思想家ボード・リヤール(Jean Baudrillard、1929-2007)的なことでいえば、人間そのものが人間を規定するときに、人間は交換する動物であるといえるくらいに交換というのはすごく重要なもの。だけど、それがあまりにも抽象化されていくと、自分たちの手の届かないものになっていくという……。
中村 交換のときに、交換されている物だけでなく、交換している人間を見なければいけないんです。お金を動かしている銀行の姿勢を見る。その人間(企業)は何をしているかを知って、心のやり取りに眼を向けたいと思うのです。
杉山 この金融ミュージアムで、小学生とか中高生が、交換の本質や金融に関連する企業の姿勢とは? を体験したり考えたりして、何か記憶の片隅に残してもらうようになっていくと、本当にここがオープンした意味が出てくると思いますね。
中村 そうですね。それと同時に、その小中学生が大人になるまで待たないで、いまの大人ももう一回、お金に心を取り戻して欲しいなと、わたしは思います。
杉山 ぜひ、そういう風にも活用して欲しい。
実は本日、日本の知の代表である中村さんとお話しすることは、かなりのプレッシャーだったんだけど、もしかすると、金融ミュージアムとかも結構、ごんべんの「誌」のような考えと重なるところがあるもしれませんね。
中村 あると思います。お金を、利子がいくらで、それをどう運用して、などだけを見ていたら重なりませんけれど、交換という原点に戻って考えていけば100パーセントつながりますよ。
やはり、金融でも専門の方がいらっしゃるわけです。専門的な金融の各論に入っていくと、そこでお金の流れとか仕組みが中心に詳しく語られるわけなのですが、その後ろに人間がいるということを忘れてはいけないと思います。
杉山 個々の生活があって。
中村 そう。生活があることを忘れる。哲学の大森荘蔵(おおもり しょうぞう 1921〜1997) 先生が、世界観を持ちなさい、その基本は生活だと教えてくださいました。最近の著作を『科学者が人間であること』(岩波新書)というタイトルにしたのもそれを考えてのことです。科学者は、テレビでも科学者用語で科学でしか語りません。
でも科学者にも、家庭がある。子供もかわいいでしょう、お料理もおいしいのを食べたいでしょう。生活があるのです。その人がどういう人か分からないと、信用しにくいですよね。だから、科学という自分の仕事を信用してもらうためにも、自分に日常の人間がいつも重なって存在しているという意識を持つことが大事ではないかなと思っているのです。
人類は一種。
共通性の上にある多様性が明日を豊かに(中村)。

杉山 中村さんには、このミュージアムに、ダイバーシティという切り口で動画参加をしていただいています。その中には「多様化していないと地球じゃない」、ということもいわれています。多様化しておくことで,地球が豊かになるっていうのが生き物の生き方であると。未来への可能性と多様性はやはり関係を感じますか?
中村 DNA研究で、はっきりいえる最大のメッセージは「人は一種だ」ということだと思っています。象はアフリカ象とインド象がいる。チョウだったら何万種もいます。ところが、人間は一種です。生きものについて科学ではっきり分かっていること、まだ少ないですけれど、ヒトは一種だということは確かです。根は一種なのですから、お互い分かり合えないはずはないですねと、生物学からいえるのです。
杉山 すごい話ですね。
中村 イスラムの人、キリスト教の人と、それぞれに文化があり、それぞれの気持ちは大事にしなければなりません。でも根はひとつなのですから、違うところもお互い認め合いながら社会をつくることはできると、わたしは信じています。
杉山 今でいうグローバリズムの考え方とは、少し異なりますか?
中村 そうですね。大切なのは、ダイバーシティだと思います。生きもの全体もたしかに多様でバラバラです。けれど、これも38億年前に戻れば根はひとつです。ダイバーシティを語るときは、「でも、そこに根っこがあるよ」ということを言わないと意味がない。
杉山 バラバラということになってしまうと・・・。
中村 はい、本当のダイバーシティは、共通性あっての多様性。バラバラとは違います。ここのミュージアム映像でも話していますが、地球は多様化の方向で動いてきました。生きものは多様化することで続いてきたのです。こっちがいいと一方にだけ行ってしまうと滅びてしまう。多様化しておくことで、地球が豊かになるというのが生きものの有り様です。いろんな生きものがそれぞれ生きるための能力を持っているのです。ただ、何千万種いる生きものの中で、ほかの生きものにはなく、人間だけが持っているのがイマジネーション=想像力。見えないことがわかる。過去を考えたり未来を考えたり。わたしたちは、新しく生まれる子供が生きる未来社会をどうしたらよいだろうと考えますね。それができるのは、人間だけです。
だから、イマジネーション=想像力を豊かに、多様な存在を認めあって生きるということがいちばん人間らしい生き方だと思っています。銀行のお仕事の中でも、地域の生活、生命や環境のことなどについても想像力をはたらかせ、豊かなお仕事をしてくださるよう願っています。
杉山 共通性あっての多様性。ダイバーシティは、いま様々な企業においても大きなテーマだし、大切に考えていいかなければいけませんね。
今日は、いいお話を聞かせていただいて有り難うございました。


杉山 恒太郎
株式会社ライトパブリシティ 代表取締役執行役員社長。大阪芸術大学 客員教授
1999年より電通においてデジタル領域のリーダーをつとめ、インタラクティブ広告の確立に寄与。トラディショナル広告とインタラクティブ広告の両方を熟知した、数少ないエグゼクティブクリエーティブディレクター。


中村桂子(なかむら けいこ)
1936年東京生まれ。理学博士 JT生命誌研究館館長 東京大学理学部化学科卒
DNAの働きから生命現象を考える分子生物学を出発点としながら、分析にとどまらず“生きている”という現象そのものを知りたいと考え、38億年の生命の歴史とその中での多様な生きものの関係を探る生命誌という新しい知の構築に挑戦。絵本『いのちのひろがり』など著書多数。

「絵巻とマンダラで解く生命誌」
青土社より発売中。
生命の38億年を目で見て感じる3つの絵物語。





